64ビット版のRaspberry Pi OSに、OpenMediaVault 6をインストールしてみました。
USBストレージを取り付けて、SMB/CIFSやNFS、Rsync対応のNASを構築できます。
管理画面は日本語対応で、共有フォルダの作成やユーザアクセス権限の設定など、Webブラウザ上ですべての管理ができるようです。RAID構築やプラグインによる機能拡張にも対応しています。
64ビット対応のRaspberry Pi 4でNASを構築したい場合、最もお勧めの構成です。
構築手順を記録させて頂こうと思います。
NAS用USBストレージの他に、起動用microSDカード必須
使用する機材は下記になります。
Raspbrery Pi 4本体
[amazonjs asin=”B0891RC99L” locale=”JP” title=”正規代理店商品 Raspberry Pi 4 Model B (8GB) made in UK element14製 技適マーク入”]NASを構築するにあたり、USB 3.0端子に対応したRaspberry Pi 4がお勧めです。また今回Raspberry Pi OSは64ビット版を使用しますので、性能を最大限引き出すことが可能です。
microSDカード
[amazonjs asin=”B07N31TTJT” locale=”JP” title=”トランセンド microSDカード 64GB UHS-I U3 V30 A2 Class10 (最大転送速度100MB/s) TS64GUSD330S”]microSDカードは、起動用のストレージとして使用します。OpenMediaVaultの仕様上、起動したストレージと、共有フォルダを作るストレージを必ず分ける必要があります。実はストレージ1つでNASを構築できないか、実際に試したのですが、失敗に終わりました。
起動用ストレージの容量は、それほど多くなくて大丈夫のようですが、32GBで構築したところ、再起動後に起動しなくなった経験がありました。64GBでは問題なく起動しました。
性能を最大限引き出せる「UHS-I U3 A2対応」を選択しましょう。U3は最低読書速度30MB/s保証、A2はランダムアクセスの速さを表します。またV30、V60のような表記がある場合、V30以上を選択しましょう。
Raspberry Pi 4のEEPROMブートローダーが最新版の場合、microSDカードではなく、USBフラッシュメモリーからOpenMediaVaultを起動することも可能です(実験済み)。しかし繰り返しになりますが、NAS用のストレージが別途必要になり、ストレージ用にUSB 3.0端子を2つ使用します。起動はmicroSDカードで問題無い気がします。
USBストレージ
[amazonjs asin=”B0918WYL3L” locale=”JP” title=”BUFFALO(バッファロー) HD-TDA4U3-B 外付けHDD USB-A接続 TOSHIBA Canvio Desktop(テレビ・パソコン両対応) ブラック [据え置き型 /4TB]”]共有フォルダ用の専用ストレージになります。複数台ストレージを接続し、各種RAIDの構成も可能のようです。
Raspberry Pi のUSB端子は電源容量に制限があるため、消費電力が大きいストレージを接続すると、動作が不安定になります。コンセント付きの3.5インチHDDを取り付ける方法が手軽でお勧めです。
2.5インチHDD/SSDを使用する場合、Y字ケーブルで別途電源を供給する必要があります。よろしければこちらの記事を御覧ください。
注意が必要なのはSSDです。SSDの機種によって、電源容量不足で動作が不安定になる場合があります。その場合、セルフパワーのUSBハブで電力を供給する必要があります。
[amazonjs asin=”B0759XCLVR” locale=”JP” title=”エレコム USB3.0ハブ/ACアダプタ付/セルフパワー/4ポート/ブラック U3H-A408SBK”]
SSDについての詳細はこちらの記事になります。
Raspberry Pi 4用電源
[amazonjs asin=”B09M715V5V” locale=”JP” title=”Geekworm Raspberry Pi 4 USB-C (Type C)電源アダプター、5V 4A 20W、 Raspberry Pi 4 /PiKVM-A3/PiKVM-A8/NASPi/Jetson nano 2GB/X735/X728/X708/X703適用”]Type-C対応、電圧5V、電源容量4A(20W)の電源をお勧めします。電源容量が少ないと、画面右上に雷マークが表示されて動作が不安定になります。必ず4A以上を供給できる電源を使用しましょう。
LANケーブル
[amazonjs asin=”B00B42H1FK” locale=”JP” title=”エレコム LANケーブル CAT6A 3m ツメが折れない 爪折れ防止コネクタ cat6a対応 スタンダード ブルー LD-GPAT/BU30″]後述の公式インストールマニュアルで確認したところ。OpenMediaVaultはWi-Fiに対応していますが、初期設定は有線LANで行う必要があるそうです。
またNAS、サーバとして運用する事を考えると、有線LANで接続したほうが、性能を最大限活かせるように思えます。
64ビット版Raspberry Pi OSへのOpenMediaVault 6構築手順
構築の手順は、次の流れになります。
- 起動用のmicroSDカード作成
- 初期設定・アップデート
- OpenMediVault 6インストール
- 管理画面ログイン
- OpenMediaVault設定(NASとしての各種設定)
Raspberry Pi 4のブートローダーEEPROMが古い場合でも。2番の手順の中で、EEPROMを最新版に更新できます。このあたり、Raspberry Piの公式OSを使用するメリットがありますね。
OpenMediaVault 6インストールの公式手順は、下記になります。こちらの手順がベースになります。
https://wiki.omv-extras.org/doku.php?id=omv6:raspberry_pi_install
では順番に進めて行きましょう。
OSはRaspberry Pi OS Lite(64ビット)を選択
Raspberry Pi Imagerで、microSDカードにOSイメージを書き込みます。
https://www.raspberrypi.com/software/
この時、必ず「Lite版」を選択します。
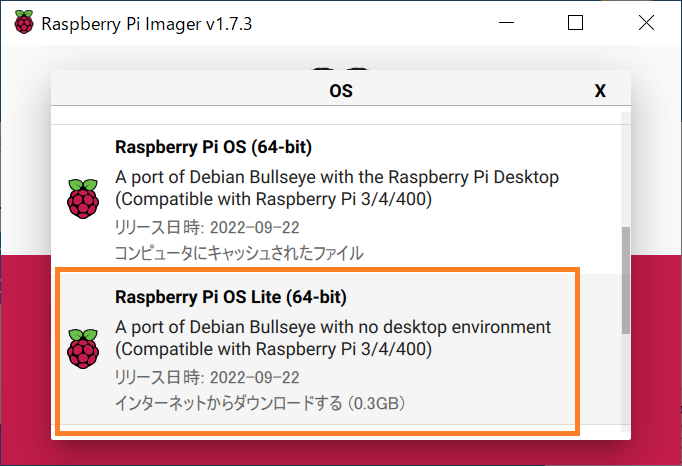 Liteではない通常版では、OpenMediaVaultインストールが進みません。(実験済み)
Liteではない通常版では、OpenMediaVaultインストールが進みません。(実験済み)
絶対にLite版を選ぶ必要がありますので、十分にご注意下さい。
またイメージ書込み前に、歯車アイコンで初期設定を行います。
ユーザを予め作成しますが、「admin」は使用できません。OpenMediVaultの管理用に予約されていますので、必ず別のユーザを作成します。別のユーザは、初期設定やOpenMediaVault以外の機能の管理に使用するかたちです。
- ホスト名 pi4nasにしてみました
- SSH有効
- ユーザ名
- 一般的にはpi等ですが、セキュリティ上他と被らないものが望ましいです
- 「admin」は予約済みのため使用不可
- ロケール
- タイムゾーン→Asia/Tokyoが選択済み
- キーボードレイアウト→「jp」と入力するか、カーソル上キーで選択
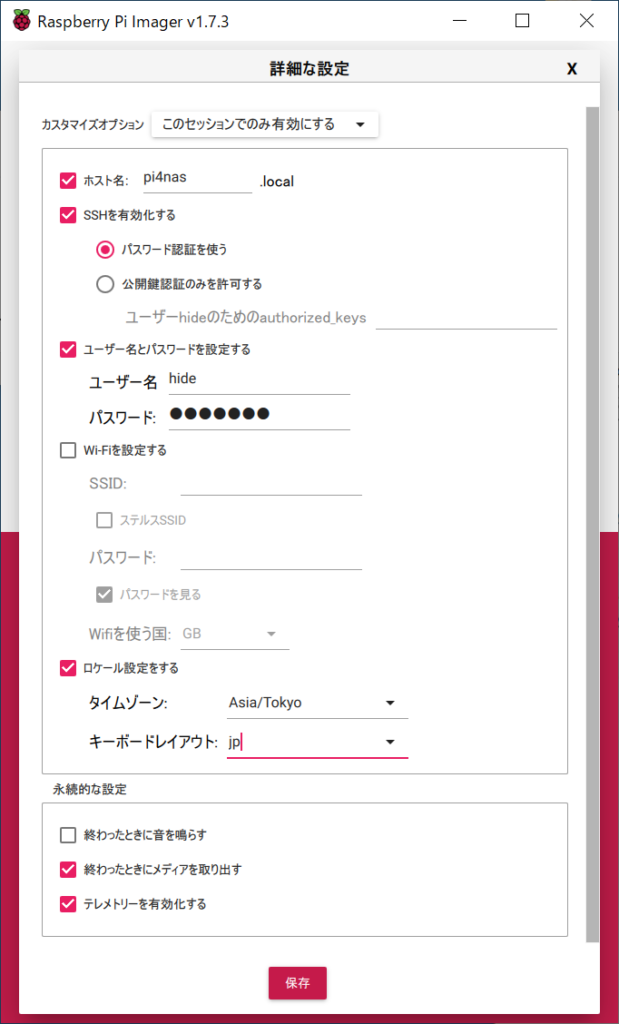 設定を保存後、microSDカードにLite(64-bit)版イメージを書き込みます。
設定を保存後、microSDカードにLite(64-bit)版イメージを書き込みます。
Raspberry Pi OS Lite(64ビット)の初期設定
Raspberry Pi 4にmicroSDカードをセットします。
このとき、USBストレージは、まだ接続しないほうが良いと思います。これはRaspberry Piがうまく起動しない場合があるためです。取り外しておきます。
ディスプレイ・キーボードを接続して初期設定することも可能ですが。
LANケーブルを接続して、別のPCからSSHで接続して初期設定しようと思います。
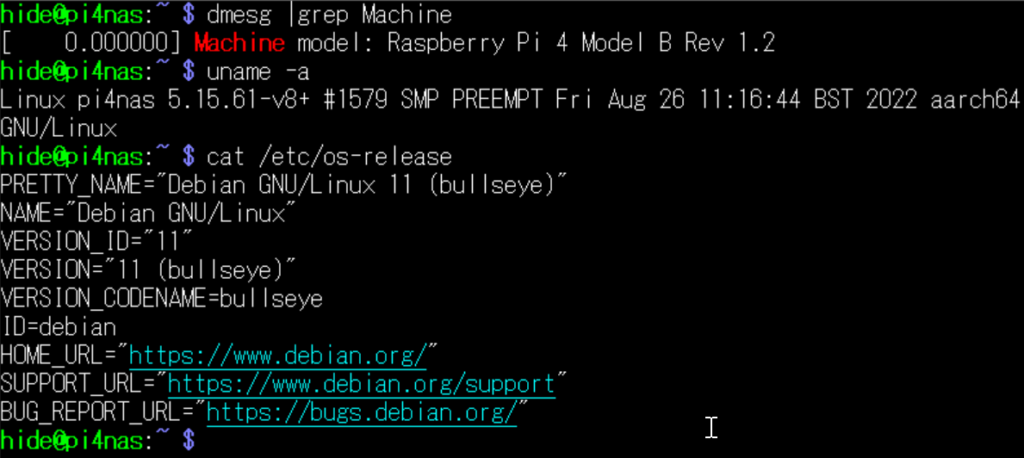 起動後、イメージ書込み前に作成しておいたユーザでログインしました。
起動後、イメージ書込み前に作成しておいたユーザでログインしました。
Wi-Fiの国設定
国設定を行わないと、ログイン時に警告が表示されるのですね。
raspi-configで行っておきました。
sudo raspi-config5 Localisation Options→L4 WLAN Country→Jキーを4回ほど押して「JP」選択
静的IPアドレス設定
※23.10.10追記:
IPアドレスの設定は、OMVインストール後に、OMVのGUIから行う必要がある、との情報が御座いました。
[blogcard url=”https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/42728-no-network-connection-after-omv-6-new-installation/”]
DHCPにてOMVインストール後、GUIから設定を行うほうが、動作が安定するそうです。
NASとして使用するということで。有線LANに接続し、静的IPアドレスを割り当てたほうが、今後使用するうえでトラブルは少ないのかなと思います。
dhcpcd.confファイルを編集して、eth0デバイスに静的IPアドレスを割当ました。
sudo vi /etc/dhcpcd.conf編集完了後、再起動すると割り当てたIPアドレスでアクセスできます。
OpenMediaVaultのインストールを始める前に、再起動して静的IPアドレスでSSH接続できるかどうか、確認しておいたほうが良いと思います。
OS更新
aptコマンドでOSを更新します。
sudo apt update
sudo apt upgrade -y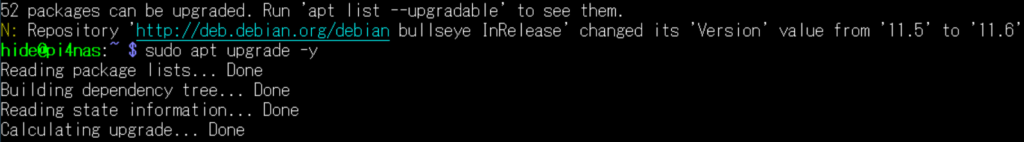 令和5年(2023年)1月現在。アップデートによりDebianのバージョンが11.5から11.6に変わりました。
令和5年(2023年)1月現在。アップデートによりDebianのバージョンが11.5から11.6に変わりました。
OpenMediaVault 6のインストールに特に影響はなく、11.6に更新しても特に問題ありませんでした。
USBストレージのパーティション削除
共有フォルダとして使用するUSBストレージのパーティションは、予め削除しておきました。
sudo cfdisk /dev/sda パーティション削除後、USBストレージは取り外しておきます。
パーティション削除後、USBストレージは取り外しておきます。
後でRaspberry Piを再起動しますが、USBストレージが接続されていると、先に進まなくなる場合があるためです。
今は取り外しておいて、あとでWeb管理画面に入ってから取り付けましょう。
OpenMediaVault 6インストール開始
それではメインのOpenMediaVault 6をインストールしましょう。
下記のコマンドになります。
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
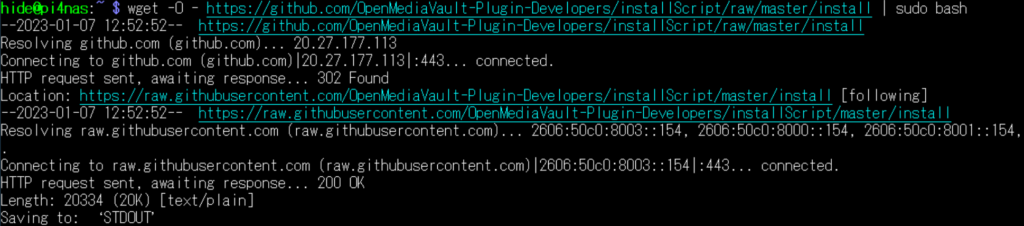 実行すると、インストールが開始され、各種パッケージのダウンロードや自動設定が行われます。
実行すると、インストールが開始され、各種パッケージのダウンロードや自動設定が行われます。
microSDカードの速度にもよりますが、30分程度かかりました。
のんびり待ちましょうね。
そして最後がこちら。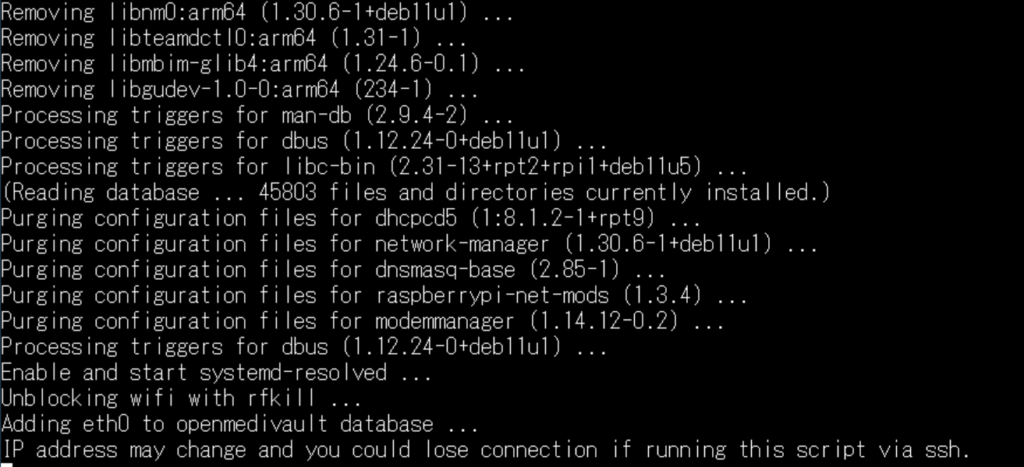 この表示のあと、SSH接続が切断され、Raspberry Piが再起動します。
この表示のあと、SSH接続が切断され、Raspberry Piが再起動します。
SSH接続が切断されたら、再起動を待つ感じです。
コンソール(ディスプレイ・キーボード)を接続している場合、そちらで再起動を確認します。
静的IPアドレスを割り当てた場合、pingで再起動完了を待ちましょう。
Raspberry Pi 自動再起動後、Webブラウザで初期設定
再起動が完了してしばらく待つと、Webブラウザで初期設定画面にアクセスできるようになります。
IPアドレスまたはホスト名.localでアクセスします。
http://pi4nas.localOpenMediaVault 6の初期設定・ファイルシステム作成
続いて、NASとしての設定に移ります。
adminログイン・メニューの日本語化
初期ユーザ/パスワードは、admin/openmediavaultのようです。
ログインできましたでしょうか?
ログインできましたら、右上User settingsアイコン→Language→日本語を選択して、メニューを日本語化してしまいましょう。
USBストレージの取り付け
それでは、Raspberry PiのUSB端子にストレージを取り付けましょう。
私は2.5インチHDDを取り付けましたが。
ファイルシステムの作成
ホーム→ストレージ→ディスクを選択しますと。
取り付けたUSBストレージが認識されています。
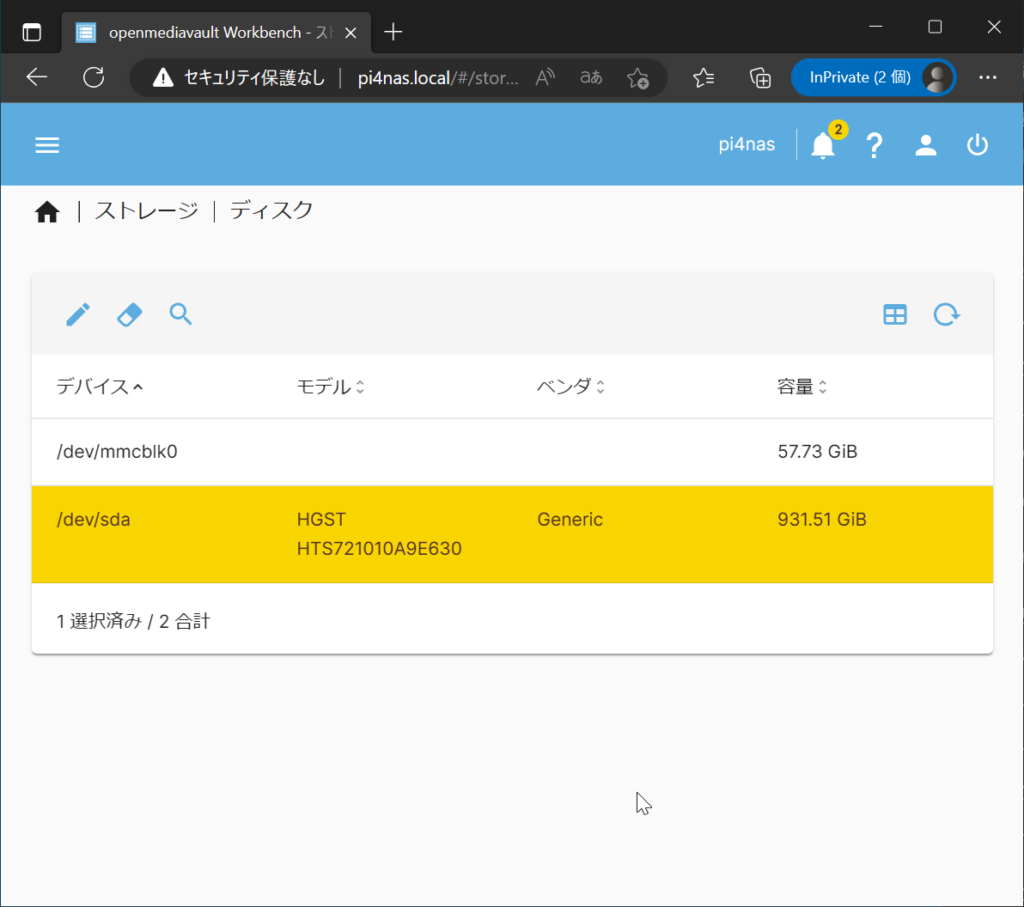 デバイスは/dev/sdaになります。複数のUSBストレージを取り付けた場合、sdb, sdc・・・のように複数認識されると思います。
デバイスは/dev/sdaになります。複数のUSBストレージを取り付けた場合、sdb, sdc・・・のように複数認識されると思います。
ストレージ→ファイルシステムに移ります。
画面左上の+アイコン→作成メニューを選択して、ファイルシステムの作成に入りましょう。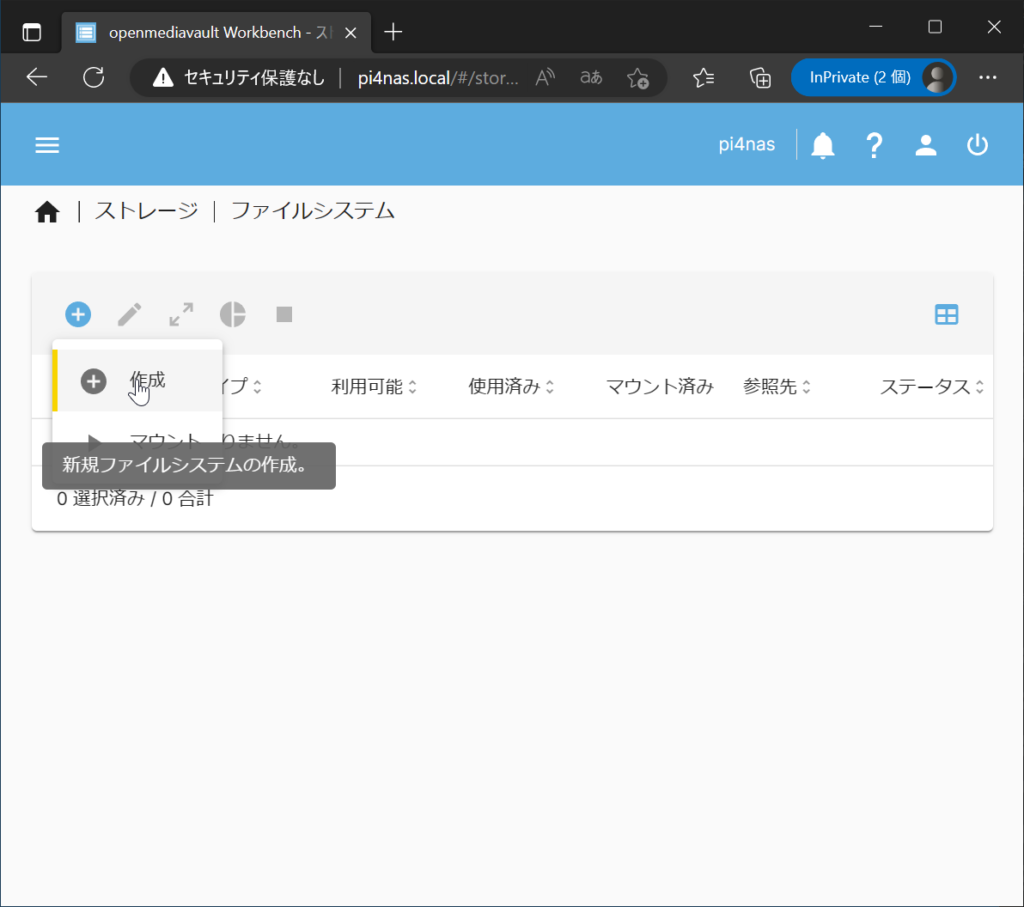
デバイス欄は、接続したUSBストレージを選択します。
タイプは既定でEXT4が選択されています。何か他に使用したいファイルシステムがあれば、6種類から選べるようです。
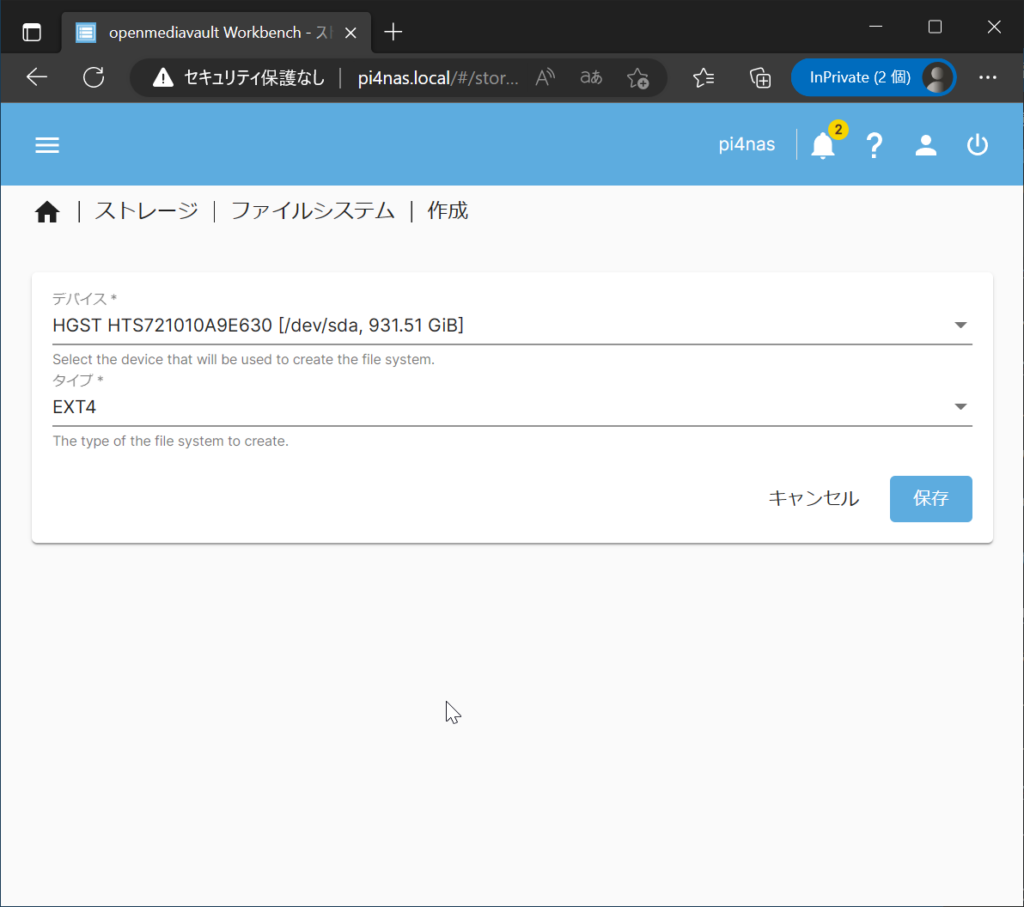 「保存」ボタンをクリックして、ファイルシステムを作成します。
「保存」ボタンをクリックして、ファイルシステムを作成します。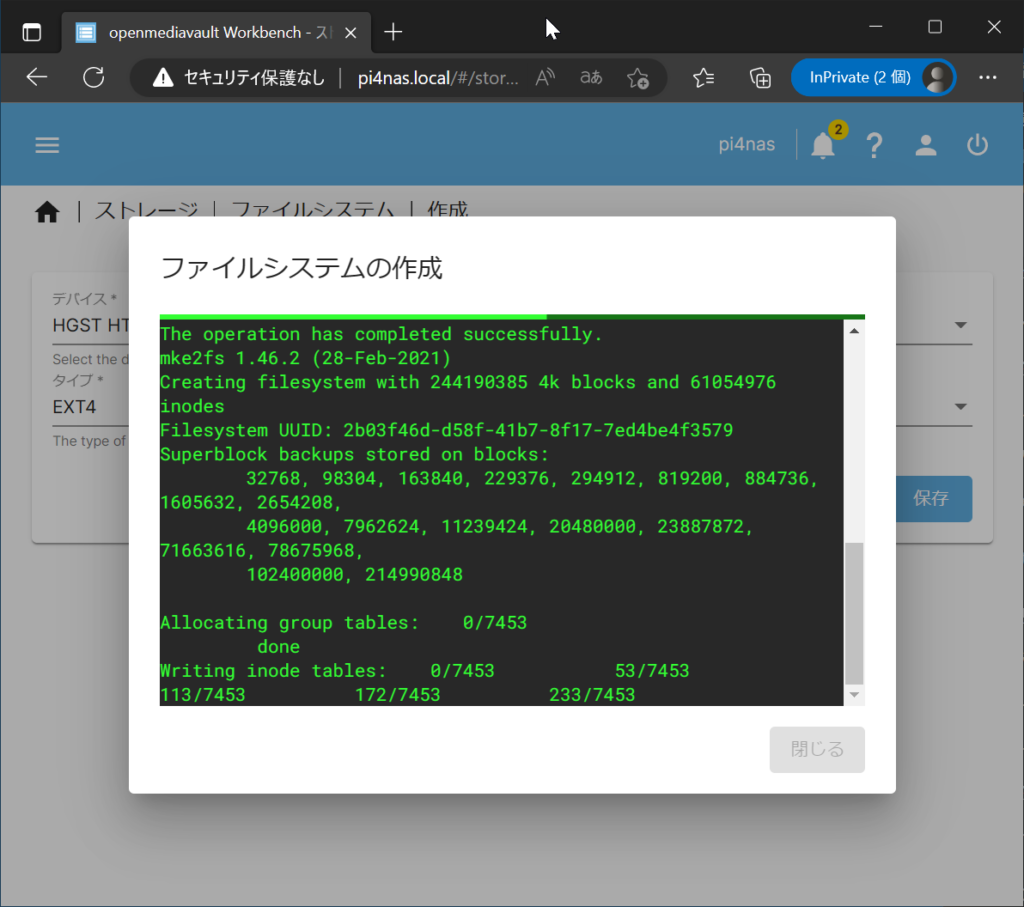
以上で、USBストレージにパーティションを作成して、共有フォルダを作成する準備ができました。
暫く待つと、ファイルシステムが作成され「閉じる」ボタンが押せるようになります。
ファイルシステムのマウント
ファイルシステム作っただけでは、マウントされないのですね。
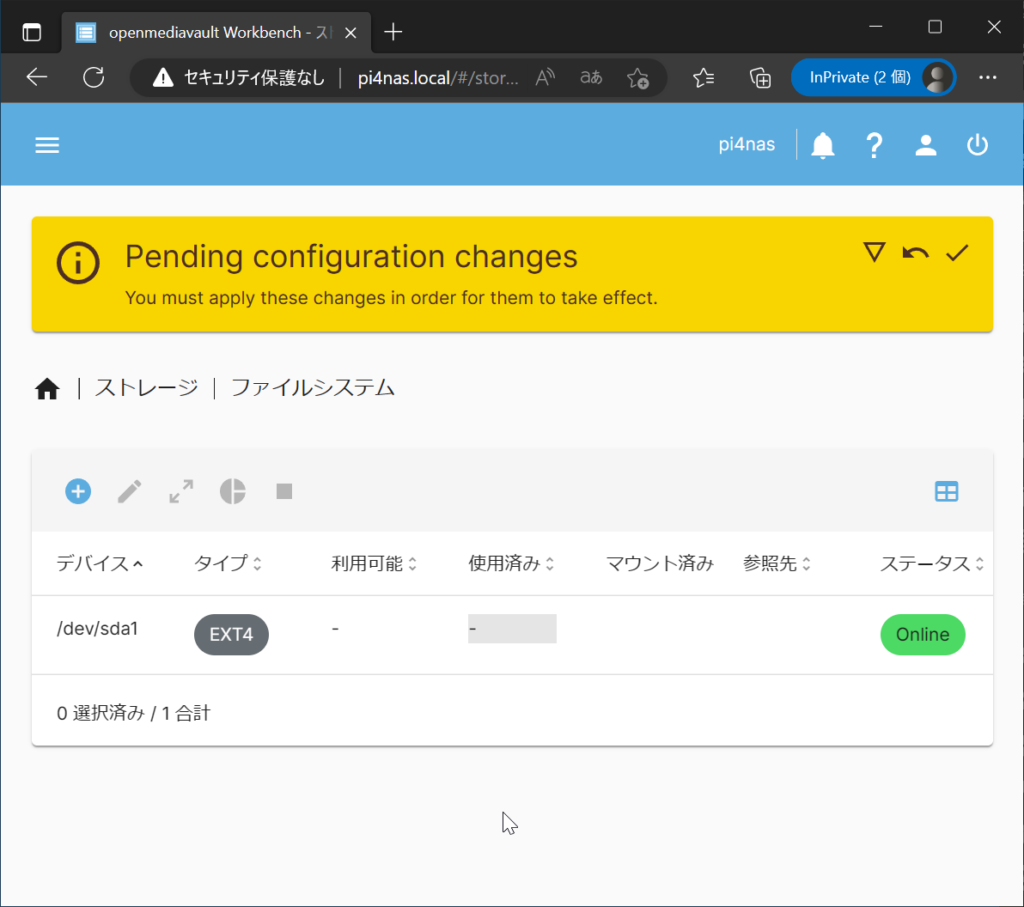 「Pending Configuration Changes」は、「変更を反映しますか?」の意味かと思います。
「Pending Configuration Changes」は、「変更を反映しますか?」の意味かと思います。
この黄色い帯が出ましたら、右端のチェックをクリックしましょう。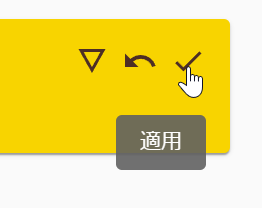 これで設定変更が反映されて、次のステップに進めます。
これで設定変更が反映されて、次のステップに進めます。
SMB/CIFS設定
SMB/CIFSサービス有効化
Windows PCからNASとして使用するために。
SMB/CIFS設定に進もうと思います。
まずはサービスを有効化します。
- SMB/CIFSサービス「有効」
- 参照可能有効
- Sendfileを使用する有効
- 非同期I/O有効
このあたりで保存→黄色い帯→チェックで反映という感じでしょうか。
共有フォルダ作成
サービスを有効にしましたが。
共有フォルダはまだ有りませんので、作る必要があります。
サービス→SMB/CIFS→共有に進みます。
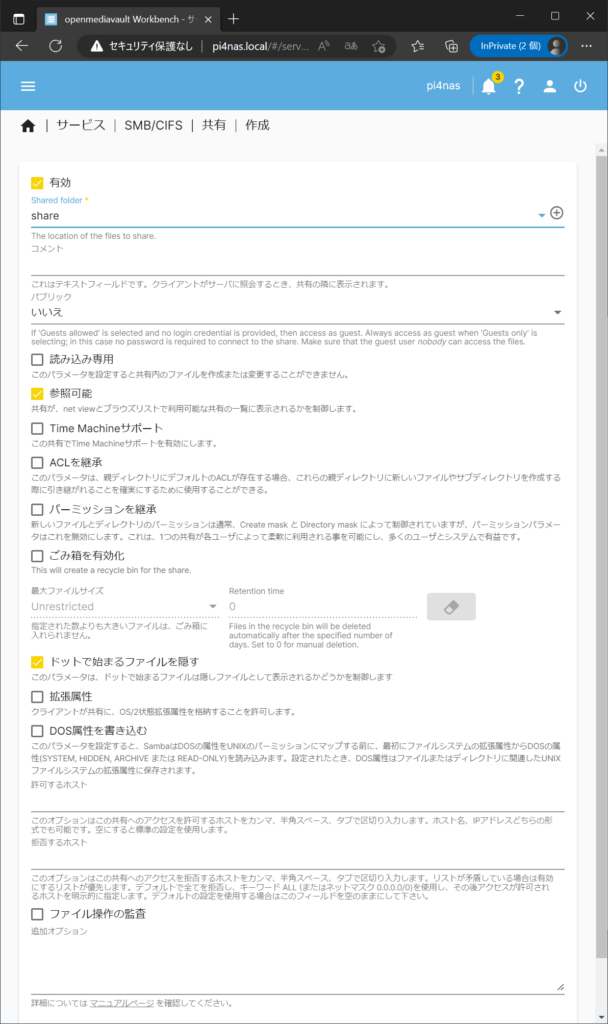 共有フォルダの作成は、さらに「Shared folder」欄の右端の+ボタンをクリックします。
共有フォルダの作成は、さらに「Shared folder」欄の右端の+ボタンをクリックします。
共有フォルダの名前を入力後、ファイルシステムを選択します。
保存で戻って。
ゴミ箱が必要な場合、「有効化」をお忘れなく。
保存→黄色い帯→適用チェックの流れになります。
ユーザのパスワード設定
最後にアクセス可能なユーザの作成/パスワード設定を行います。
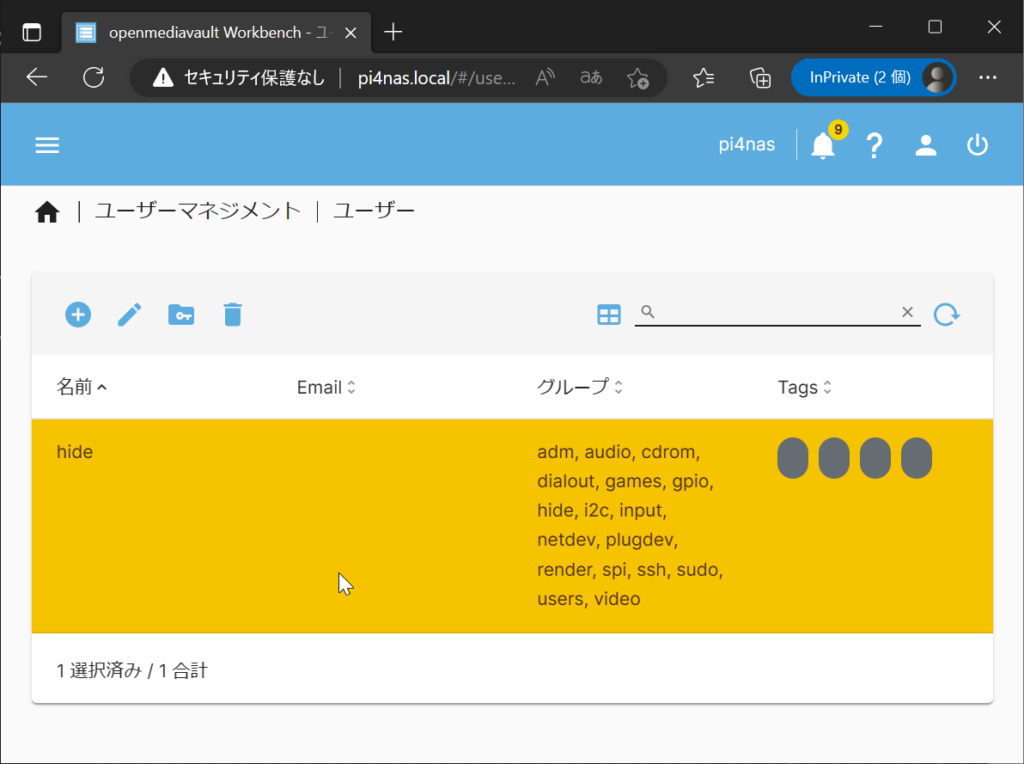 既にユーザを作成してある場合でも、SMB/CIFSアクセスのために、パスワードを再度設定する必要があるようです。
既にユーザを作成してある場合でも、SMB/CIFSアクセスのために、パスワードを再度設定する必要があるようです。
画面左上の編集(ペンのアイコン)から、ユーザの編集画面に移ります。
別途、ユーザの追加が必要な場合、続けて追加しておきましょう。
以上で基本的なNASの設定が完了しました。
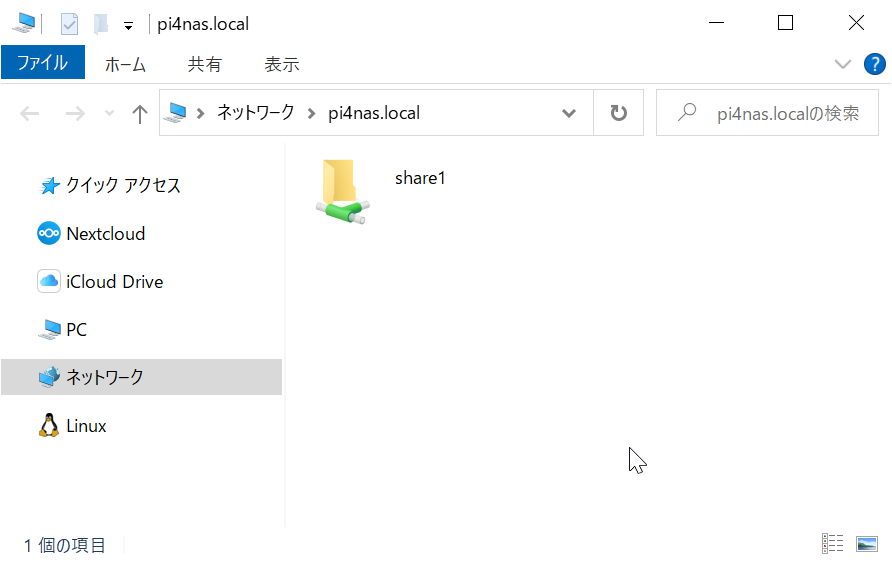 他のPCから、SMB/CIFSサーバとして、Raspberry Pi 4にアクセスが可能になったかと思いますが、如何でしょうか?
他のPCから、SMB/CIFSサーバとして、Raspberry Pi 4にアクセスが可能になったかと思いますが、如何でしょうか?
ファイルの転送速度測定
Windows PCからNASとしてアクセスした場合の、ファイルの転送速度を測定してみました。
次の環境になります。
- Windows PCとRaspberry Piを、ギガビット・スイッチに接続
- スイッチは家庭用の5ポートモデル
- Raspberry PiのUSB 3.0端子に、2.5インチHDD 容量1TBを接続し、NAS用ストレージとして使用
- 起動用メディアは、microSDカード容量64GB UHS-I U3対応。
測定は、CrystalDiskMarkさんを使用させて頂きました。
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/
フォルダーの選択→NASの共有フォルダを指定しました。
測定結果は次のようになりました。
Raspberry PiのUSB 3.0端子は、最大5Gbpsの仕様ですが。
やはりGigabit Ethernet、1000BASE-Tの実質的な転送速度が100MB/s前後で、そちらが転送速度の最大値になっている感じでしょうか。
PCを1台のみ接続して測定しました。複数のPCを接続した場合の結果は変わるのだと思いますが。
おうちLANで、小規模で使用する場合は、十分に実用的な速度が得られる事がわかりました。
NAS構築お疲れ様でした!
十分に実用的な速度で動いている、ということがわかりましたが。機能面につきまして。
今回はSMB/CIFSサーバでしたが。標準の状態で、FTP、NFS、RSyncサーバとしての設定が可能です。さらに、Extrasによる機能拡張が可能です。
またExtras以外に、Dockerによる機能追加も可能です。Nextcloudサーバ機能をOMV管理下のDockerで動かすことも可能のようです。
64ビット版の公式Raspberry Pi OSで動かしているということで。今後もOSが継続的サポートされると思いますので、長期的な運用が可能かと思います。
Raspberry PiでNASを作りたい場合、最もお勧めの方法となります。※令和5(2023)年1月現在
ぜひご活用下さい![amazonjs asin=”B07X71KQDR” locale=”JP” title=”WD デスクトップHDD 12TB USB3.0 WD Elements Desktop 外付けハードディスク / WDBBKG0120HBK-JESN 2年保証”]
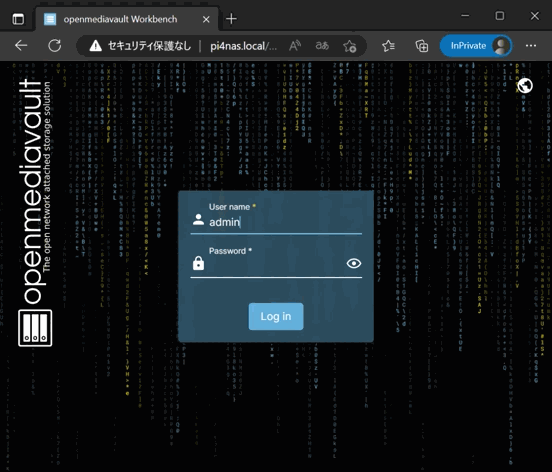
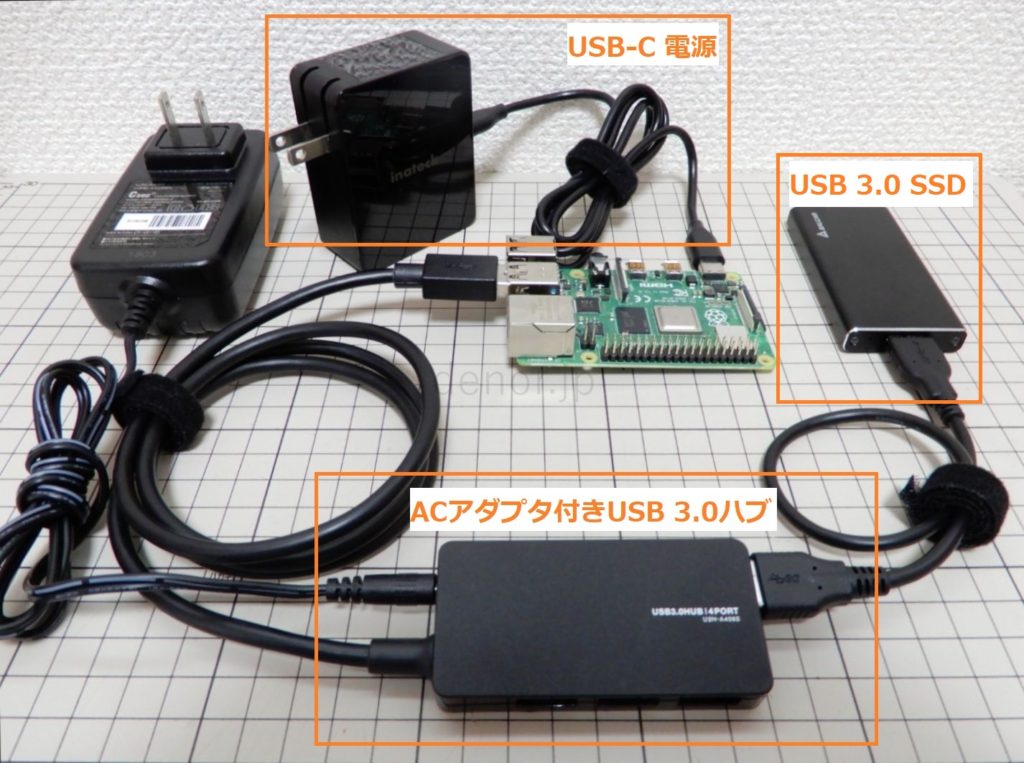
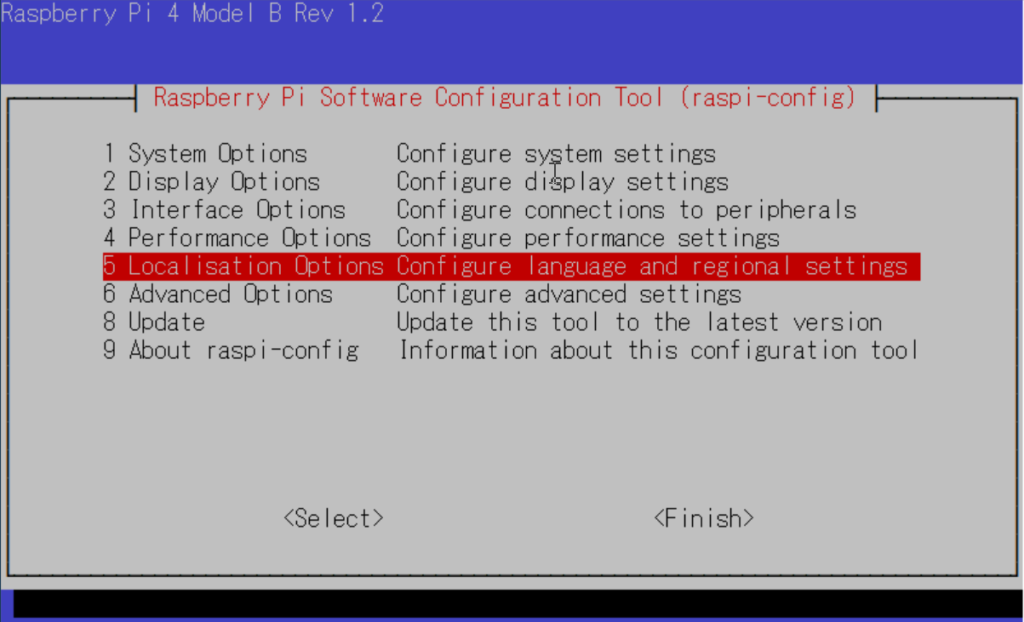
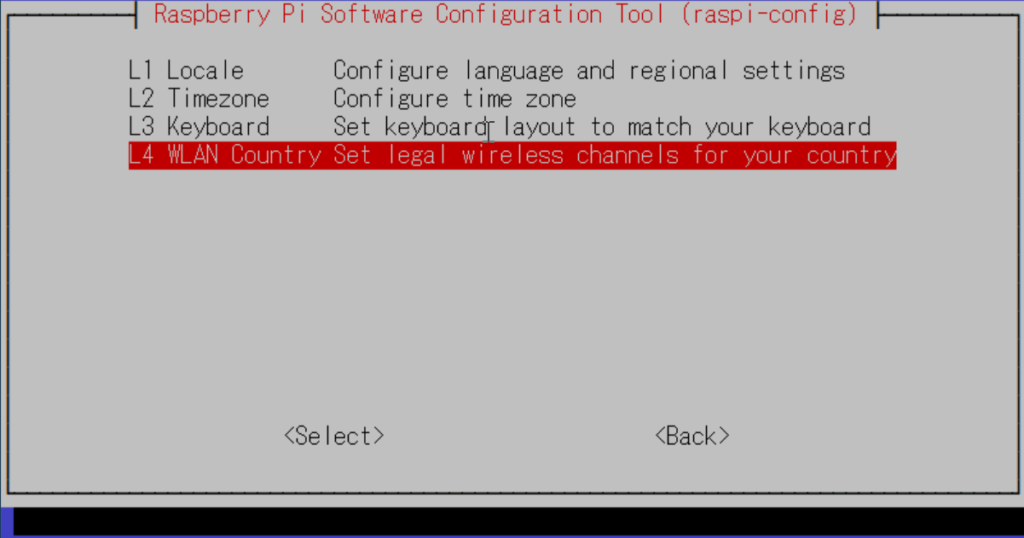
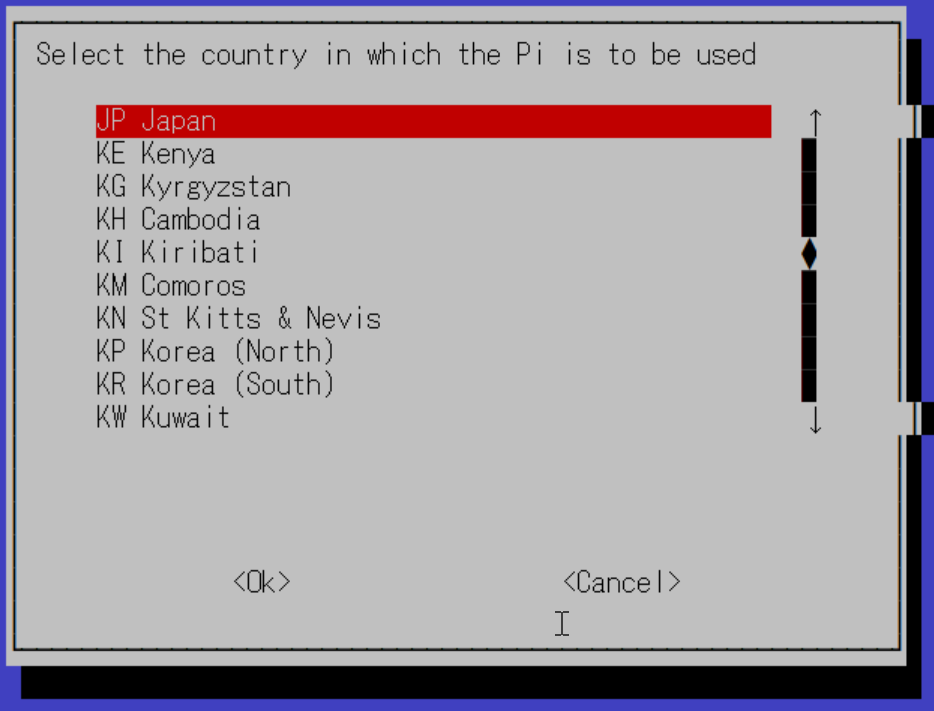

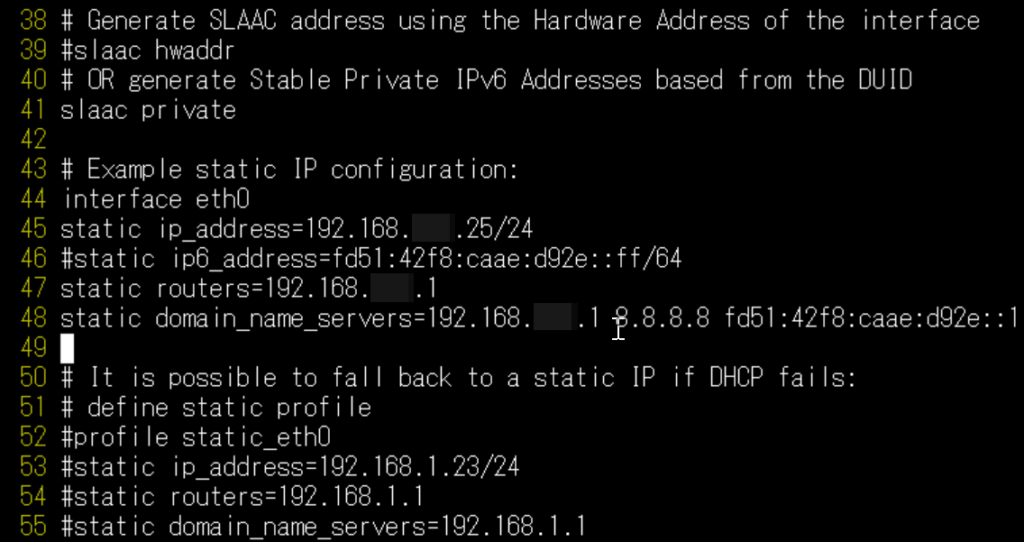
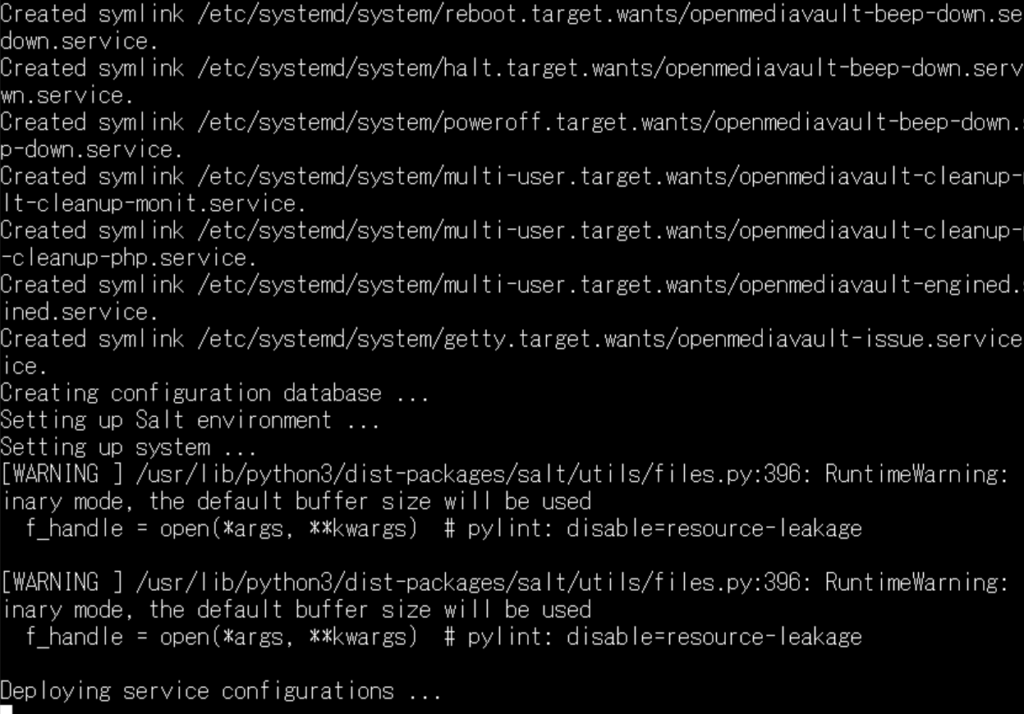
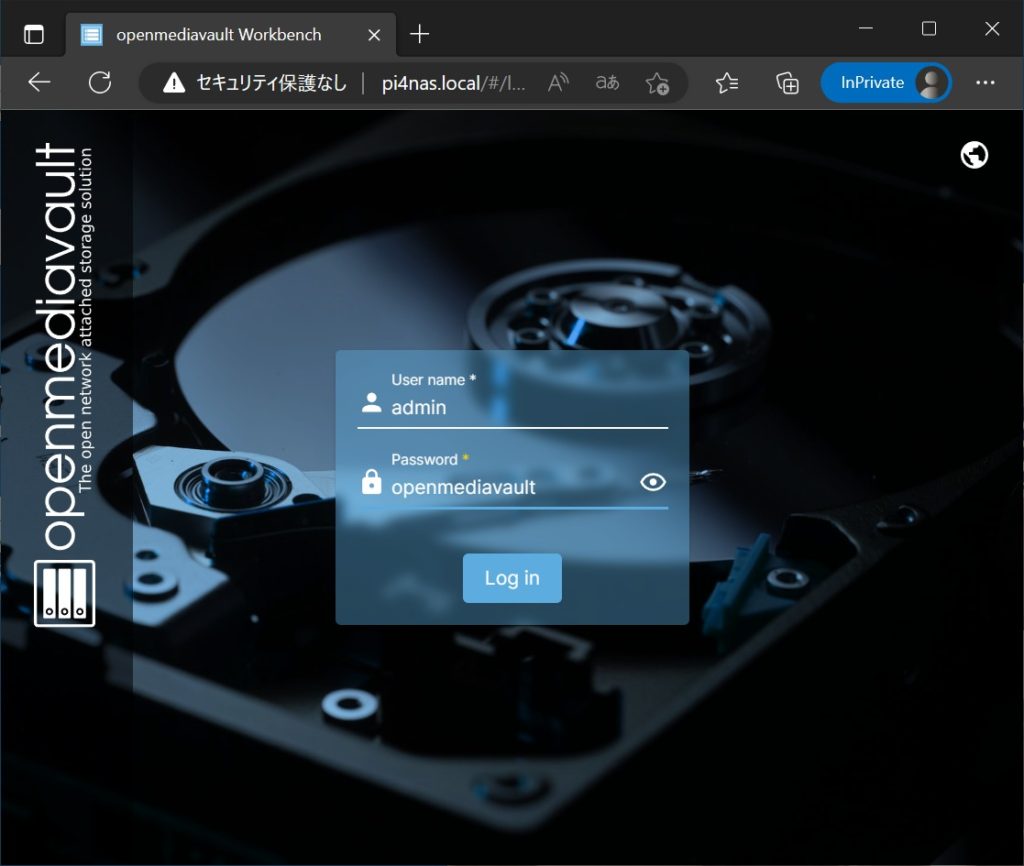
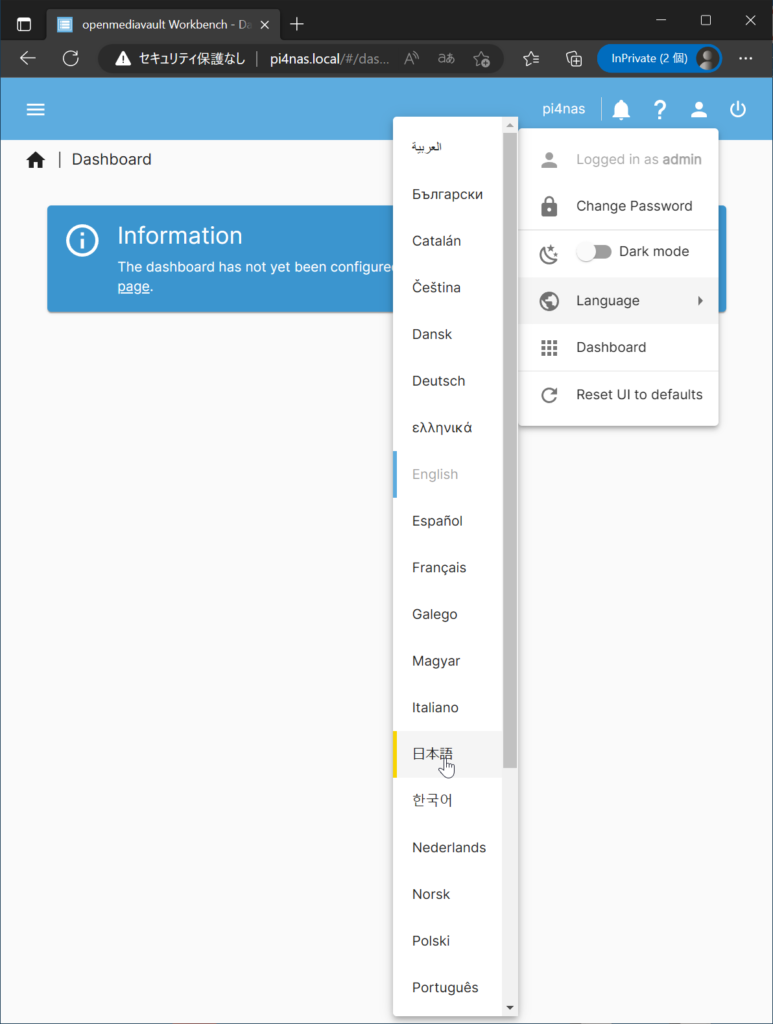
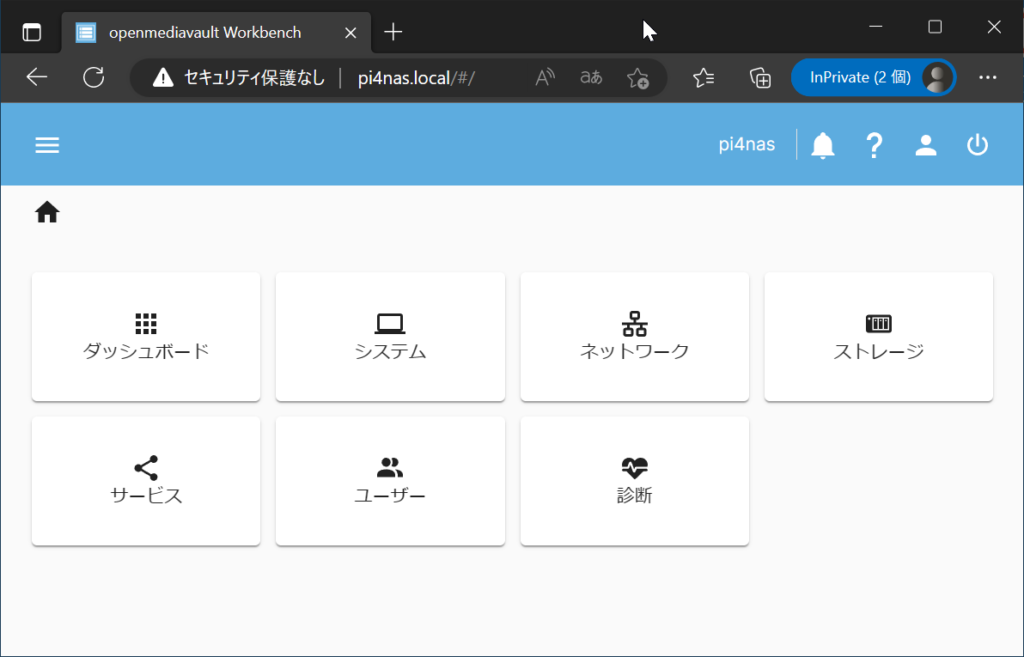

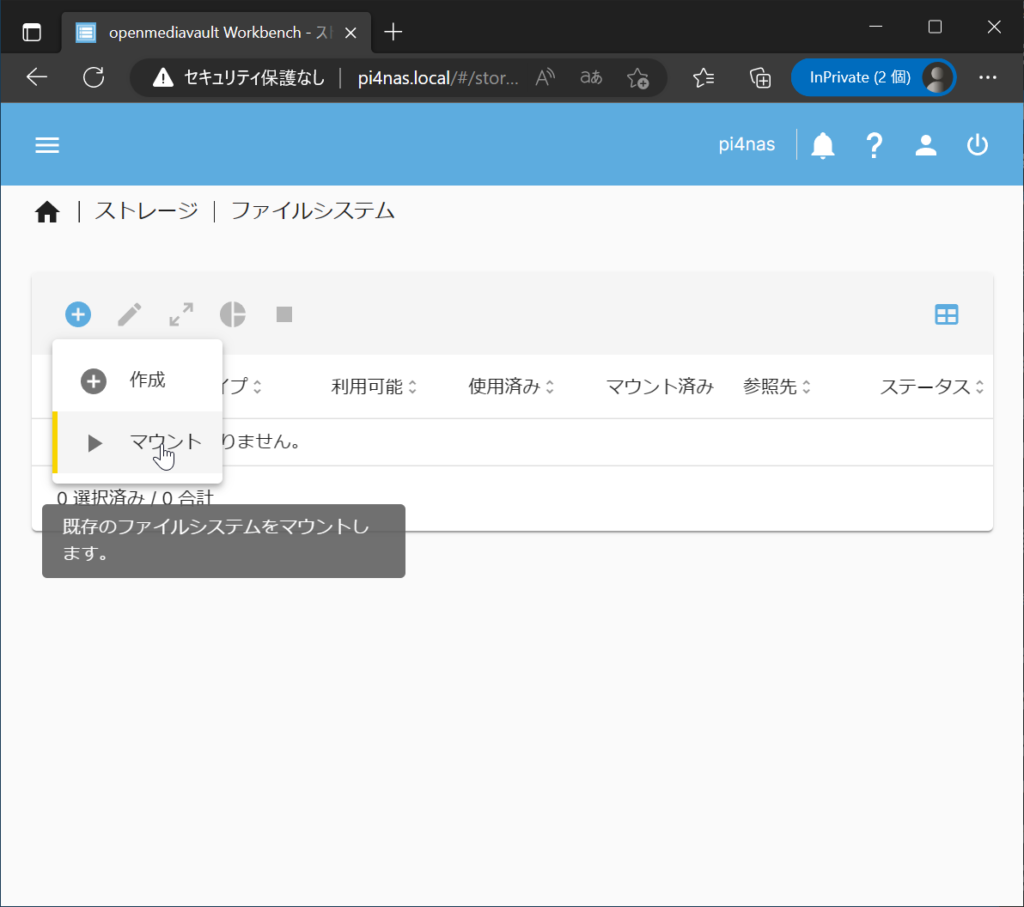
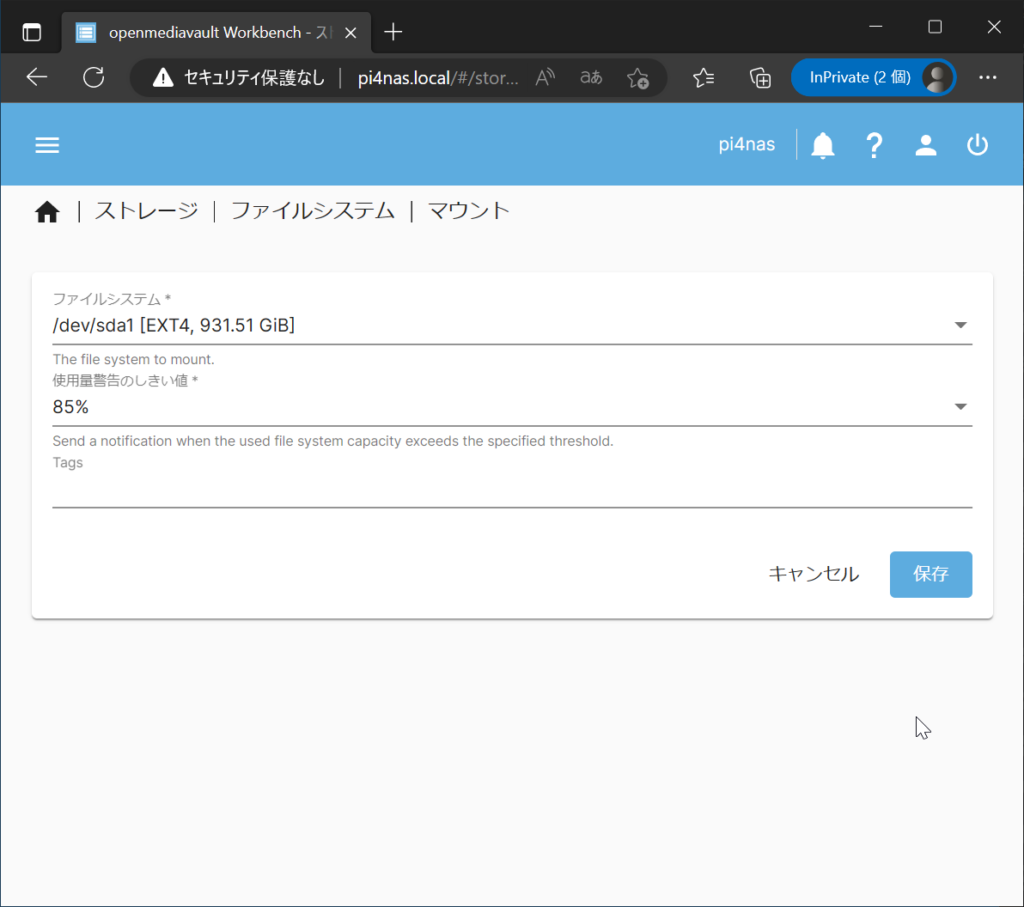
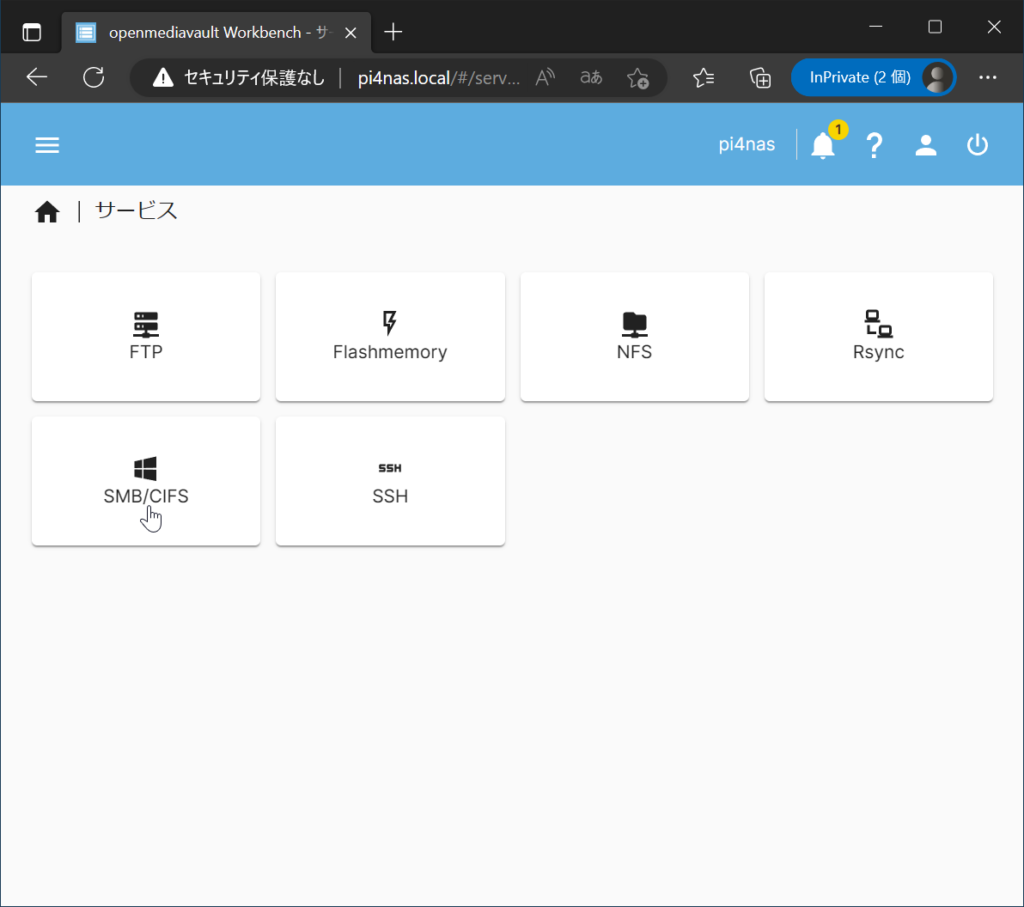
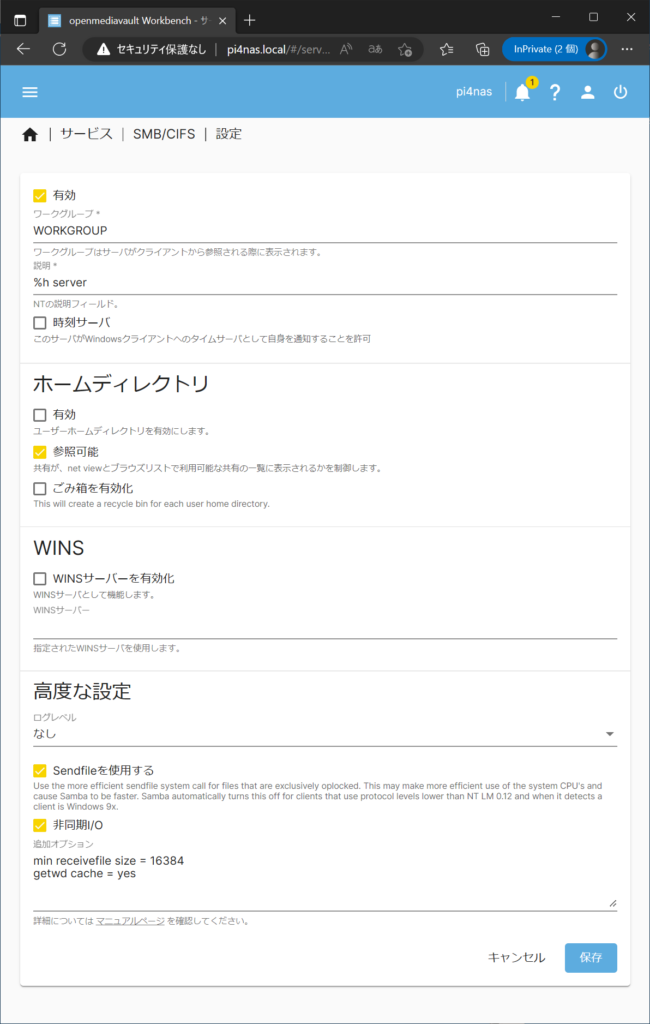
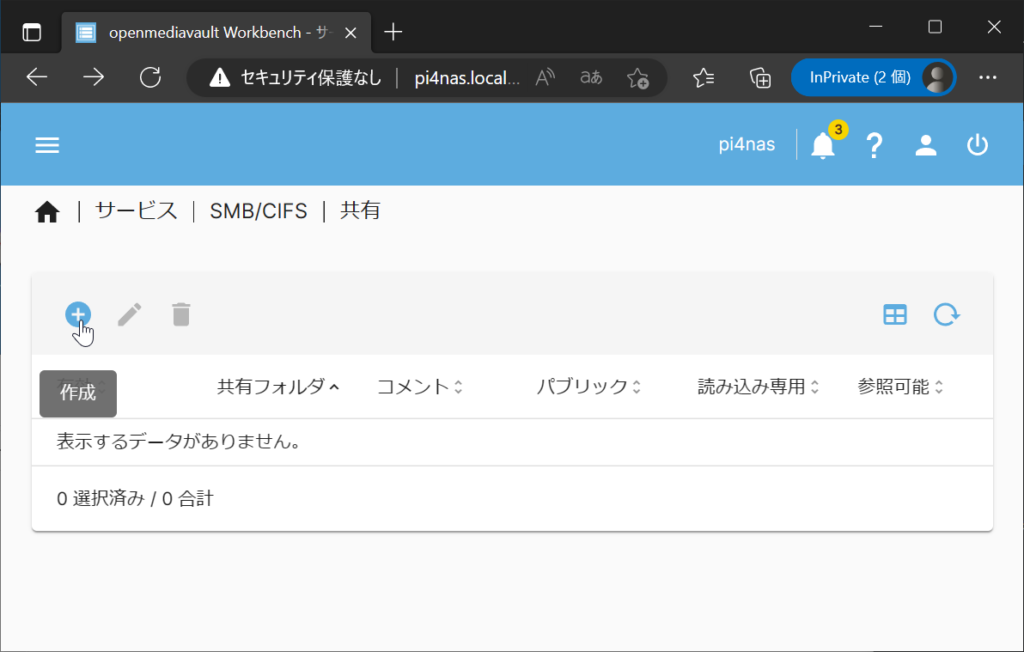
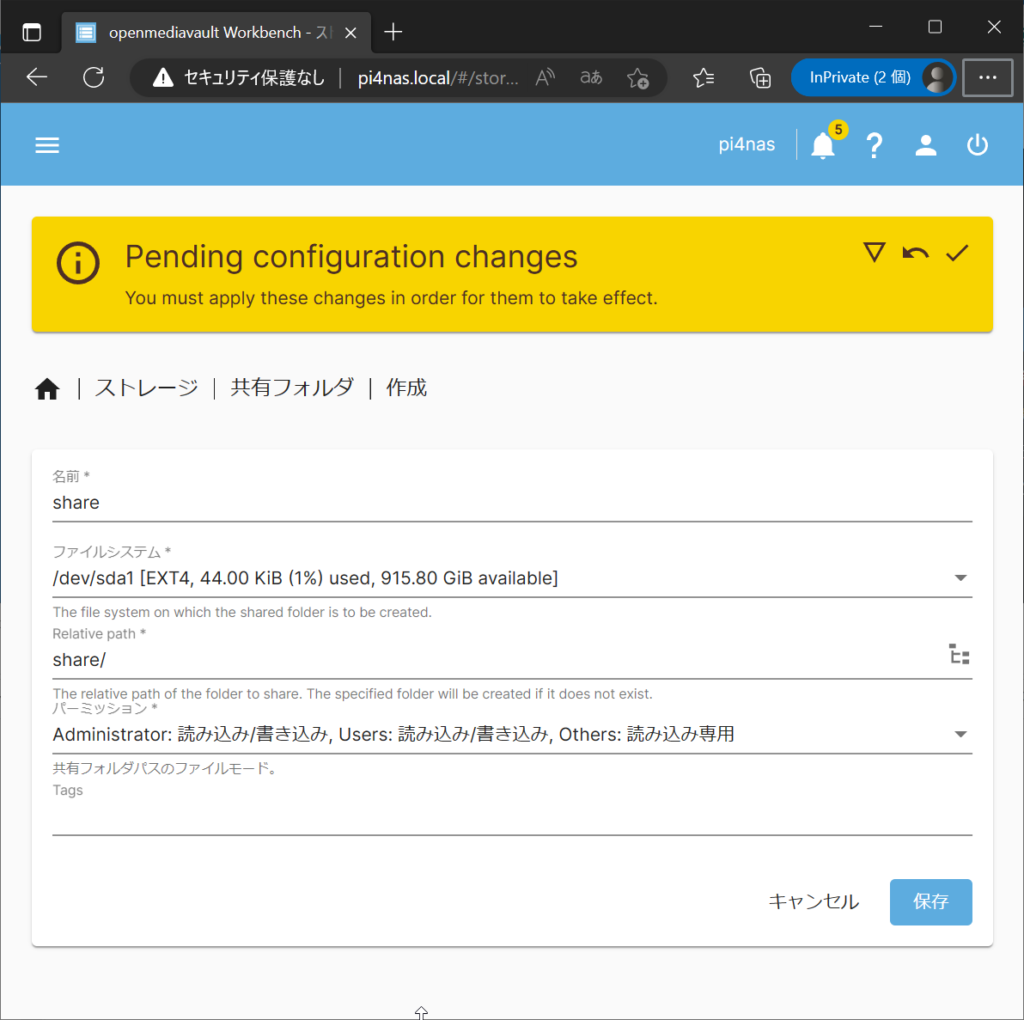
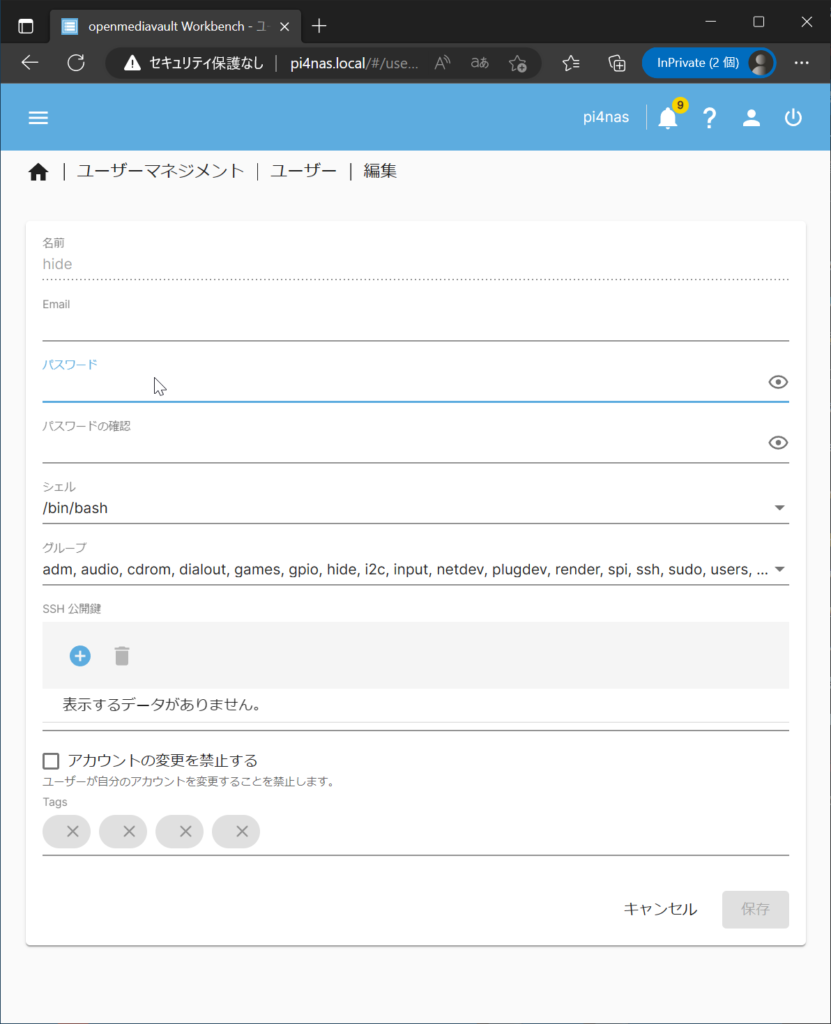

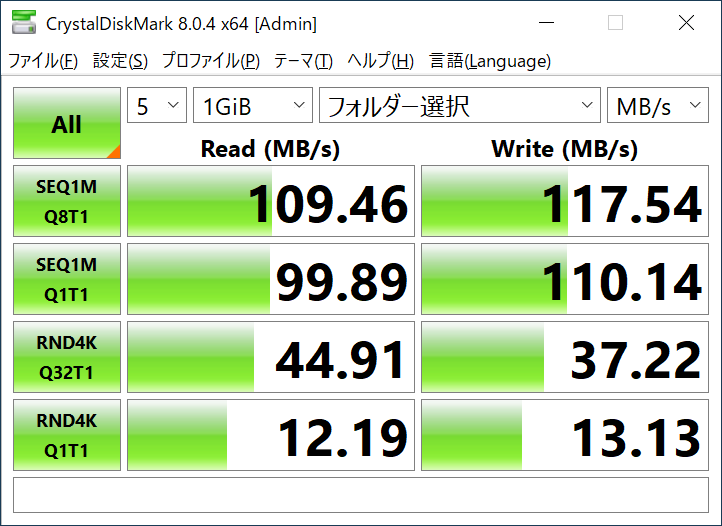
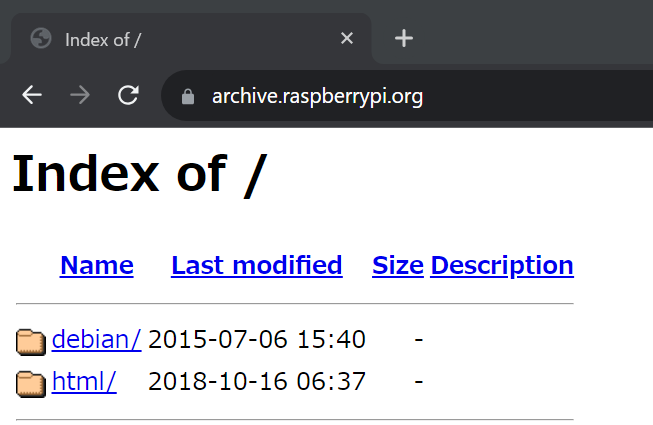
コメントを残す